過去のプレスリリース(2008)
| 2008年 | ||
| 研究室名 | タイトル・記事掲載メディア | |
| 2008/12/29 |
日刊工業新聞 平成20年12月29日(月) | |
| 細野・神谷研究室 |
今年の「夢を与えた研究者」 細野教授が選ばれる! |
|
鉄を主成分とする新しい高温超電導物質発見の研究成果が認められ、細野秀雄 教授が 2008年の「夢を与えた研究者」に選ばれました! 「夢を与えた研究者」は文部科学省科学技術政策研究所が平成5年から実施しているもので、科学技術の振興や普及に顕著な貢献があり国民に夢を与えた研究者を毎年選んでいます。 2008年は10組の研究者・グループが選ばれ、細野教授の研究成果・業績が東京・上野の国立科学博物館で展示されることになりました。 |

|
|
|
「Nature Physics」(電子版)論文掲載おめでとうございます! 2008年12月21日(英国時間)公開 |
||
| 2008/12/21 笹川研究室 |
高温超伝導の落第生からメカニズム解明の本質に迫る - 擬ギャップに2成分あることを発見 - |
|
|
笹川崇男 准教授と応セラ研共同利用研究のグループは、銅酸化物高温超伝導体のメカニズム解明への有力な実験観測に成功しました。 今回の成果を例えるならば、「超伝導の落第生のDNA観察から、優等生になるためのヒントが見えてきた」ということになります。 本研究では、似たような化学組成で同じ結晶構造と電子濃度を持つにも関わらず、高温超伝導になる物質とならない物質があることに着目しました。 その両者の電子状態を、電子の運動方向と運動エネルギーの関係を直接観察できる角度分解光電子分光法と呼ばれる最先端技術を駆使して調べたところ、次のことがわかりました。 (1)超伝導にならない物質も、エネルギーギャップを持つ。 (2)この擬ギャップには、電子の運動方向によって、生成原因の異なる2成分が存在する |
||
今後の研究により、第2の成分のエネルギーギャップの正体を明らかにし、電子対の足並みが乱されている原因を究明することによって、なぜ超伝導の落第生になってしまったのか、ひいては、どうすれば優等生になれるのかというヒントが得られるものと期待しています。 本研究成果は、英国科学会誌「Nature Physics」(オンライン版)で、2008年12月21日(英国時間)に公開されました。 また、本研究成果とネイチャー・フィジクスへの論文掲載を報じる記事が、12月22日の日本経済新聞に掲載されました。 |
Nature Physics AOP Letters (Published online: 21 December 2008 | doi:10.1038/nphys1159 ) Energy gaps in the failed high-Tc superconductor La1.875Ba0.125CuO4 論文を閲覧される場合は 下のリンクをご利用下さい。 http://dx.doi.org/10.1038/nphys1159 |
|
| 日本経済新聞<朝刊> 平成20年12月22日(月) |
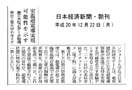
|
|
|
室温超電導実現 可能性を示す |
||
| 2008/12/19 |
Breakthrough of the Year 2008 (Science 19 December 2008) | |
| 細野・神谷研究室 | 細野秀雄 教授 らが発見した鉄系新型高温超伝導体が 米国科学誌サイエンス の2008年「科学的進歩ベスト10」に選ばれました。 |
|
|
"Breakthrough of the Year" は、米国科学誌サイエンスが毎年その年を通して科学的進歩が顕著だった研究成果のベスト10を選び出して紹介するものです。 2008年の研究成果ベスト10の第4位に鉄系新型高温超伝導体が選ばれ、サイエンス誌上で紹介されています。 <Breakthrough of th Year 2008> Science 19 December 2008: vol.322, no.5909, p.1768 (DOI: 10.1126/science.322.5909.1768) |

|
|
|
また、2008年のベスト10に選ばれたことを報じる記事が新聞各紙に掲載されています。 |
||
| 朝日新聞<朝刊> 平成20年12月19日(金) |

|
|
|
米誌選出 08年の10大科学成果 |
||
| 日刊工業新聞 平成20年12月19日(金) |
|
|
|
科学の進化ベスト10 |
||
| 日本経済新聞<朝刊> 平成20年12月19日(金) |
|
|
|
米科学誌 今年の10大研究成果選ぶ |
||
| 毎日新聞<朝刊> 平成20年12月19日(金) |
|
|
|
科学的進歩ベスト10 |
||
| 2008/12 |
This month's Emerging Research Front Paper (December 2008) | |
| 細野・神谷研究室 | 細野秀雄 教授 の論文がトムソン社の高被引用文献 ( Highly Cited Papers ) として紹介されました。 |
|
| 今年2月に JACS (Journal of the American Chemical Society) の電子版に公開された論文が、トムソン社の Highly cited papers として 2008年12月の This month's Emerging Research Front Papersに著者インタビューとともに紹介されました。 細野教授の論文が契機となって、新型高温超電導体の研究ブームが起こり、現時点で引用数が200を超え、他の3編の論文と合わせると400近く引用されています。 |

|
|
|
<インタビュー記事> ScienceWatch.com This month's Emerging Research Front Paper (December 2008) |
||
| http://sciencewatch.com/dr/erf/2008/08decerf/08decerfHoso/ | ||
|
<原著論文> J. Am. Chem. Soc., ASAP Article (Web Release Date: Feb. 23, 2008) |
||
| Iron-Based Layered Super-conductor La[O1-xFx]FeAs (x=0.05-0.12) with Tc = 26 K 論文を閲覧される場合は下のリンクをご利用下さい。 doi:10.1021/ja800073m |
||
| 2008/11/ 4 |
NHK総合テレビ 「爆笑問題のニッポンの教養」 2008年11月 4日(火)放送 | |
| 細野・神谷研究室 | NHK総合テレビ「爆笑問題のニッポンの教養」において、細野秀雄 教授 のセメント原料C12A7や鉄系高温超伝導体といった先駆的な研究成果が 『21世紀の錬金術師』 というサブタイトルで紹介(2008年11月4日23:00~23:30 放送) されました。 対談で、細野教授の研究姿勢や普段のインタビューでは聞くことができない本音などが語られています。 どのような内容だったのか、ご興味がおありの方は番組ホームページをご覧下さい。 |
|
| 2008/10/23 |
化学工業日報 平成20年10月23日(木) | |
| 安田榮一名誉教授 |
石川カーボン科学技術振興財団 「08年度 表彰・助成金贈呈式開催」 |
|
安田榮一名誉教授(元・応セラ研所長,教授) が2008年度石川カーボン賞を受賞し、去る10月21日に開催された贈呈式の模様が紹介されました。 《関連記事》 教職員の受賞・表彰(2008年) |

|
|
| 2008/10/23 | 日経産業新聞 平成20年10月23日(木) | |
| 客員研究部門 |
爆薬・数式 リアルさ追求 |
|
片山 雅英 客員教授 がフジテレビ系列で放送されたドラマ「ガリレオφ」の科学監修を務め、人気ドラマを裏で支えたスペシャリストとして日経産業新聞の「ヒット案内人」コーナーで紹介されました。 ドラマの主人公が殺人事件の謎解きをする際は、成形爆薬の爆発現象を解析する数式やチャートに実際の数値解析に使用するものを使い、背景に無造作に置かれた蔵書類も 片山客員教授が専門書を貸し出すなど、科学監修としてのアドバイスだけでなく、リアリティを追求するために尽力したことがドラマのヒットにつながっていると紹介されています。 |

|
|
| 2008/10/ 9 |
日経産業新聞 平成20年10月 9日(木) | |
| 笹川研究室 |
ダイヤで高効率LED 電気を光に変換 内視鏡など目指す |
|
笹川崇男 准教授の研究グループがダイヤモンドを使って高効率発光ダイオード(LED)素子の最適条件を理論計算で突き止めることに成功しました。 ダイヤモンドの電子構造は電気を光に変換する効率が極めて低いことが知られていますが、ダイヤモンドと同じsp3型の混成軌道を持つダイヤ分子「アダマンタン」(C10H16 。ダイヤモンドの基本骨格に水素が結合した分子)の電子構造を計算したところ、LED などに使う半導体材料と同じ電子構造に変わることが判明しました。 |

|
|
この電子構造では理論上、電気エネルギーのエネルギーを100% 光エネルギーに変換することができ、理論計算でアダマンタンの場合、波長180ナノメートルの紫外線が出るという結果が算出されました。 アダマンタンが2個、3個繋がったダイヤ分子では、それぞれ波長190ナノメートル、200ナノメートルの紫外線を出せることが判明しており、米国のベンチャー企業と協力して、今回の理論計算をもとに紫外線ダイヤLEDの開発に取り掛かることになっています。 波長280ナノメートル以下の紫外線は細胞を壊す力があり、紫外線ダイヤLEDが実用化すれば、内視鏡の先端にLEDを装着してガン治療を行うことができる新しいタイプの医療器具実現が期待されています。 本研究成果は、米国物理学協会の学術雑誌「Journal of Applied Physisl」に 2008 年10月 1日(米国時間)公開されました。 |
Journal of Applied Physics 104, 073704 (2008) A route of tunable direct band-gap diamond device: Electronic structures of nanodiamond crystals 論文を閲覧される場合は 下のリンクをご利用下さい。 doi:10.1063/1.2986637 |
|
| 2008/10/ 7 | 東京新聞 平成20年10月 7日(火) | |
| 細野・神谷研究室 |
超電導の 『新大陸』 探る 鉄系物質で再フィーバー 応用の広さに期待 |
|
細野秀雄 教授 らの研究グループによる鉄系新型高温超電導体の発見で超電導物質探索が再フィーバーしています。 2008年 2月の発見以来、世界中で研究が始まり、新型超電導物質発見時の「鉄・ヒ素・ランタン・酸素」の四元素系は類似する性質を持った別の元素に置き換えが可能なこと、また四元素から酸素を除いた三元素や鉄とセレンなどの二元素でも超電導が発現することも判明しました。 鉄系高温超伝導体の4種類の構成元素すべてが似た性質の元素に置き換え可能であり、その組合わせ次第で様々な可能性があるだけでなく、従来の銅酸化物系に比べて加工が容易であり、超電導物質の線材など実用化にも大きな期待と注目が集まっています。 |

|
|
| 2008/ 9/11 | 日経産業新聞 平成20年 9月11日(木) | |
| 細野・神谷研究室 |
21世紀の気鋭 高臨界温度物質に挑む |

|
2008年9月11日付け日経産業新聞のシリーズ「21世紀の気鋭」で、細野秀雄 教授 の下で研究する神原陽一さん(JST研究員)が紹介されています。 神原研究員は細野研究室で鉄を含む層状物質の研究・開発に取り組んでおり、様々な成功と失敗をを経て鉄系新型高温超電導物質の発見に成功しました。 細野教授の研究チームに参加してから新型高温超伝導物質を発見するまでが紙面で消化されています。 |
||
| 2008/ 9/ 4 | 日経産業新聞 平成20年 9月 4日(木) 化学工業日報 平成20年 9月 4日(木) |
|
| 細野・神谷研究室 | 日経産業新聞 平成20年 9月 4日(木) |

|
|
単結晶薄膜を作製 -新型の高温超伝導物質 性能向上に貢献- |
||
| 化学工業日報 平成20年 9月 4日(木) |

|
|
|
鉄系新超電導物質でエピタキシャル薄膜 デバイスへの応用展開 加速 |
||
| 科学技術振興機構(JST)と東京工業大学の共同発表 平成20年 9月 3日(水) | ||
|
鉄系新超伝導物質のエピタキシャル薄膜の作製に成功 -デバイス応用へのブレイクスルー- |
||
細野秀雄 教授(フロンティア研究センター) らの研究グループが鉄系新型高温超電導体の単結晶薄膜の作製に世界で初めて成功しました。 これまで新型高温超伝導物質の研究は主に多結晶体を用いて行われており、単結晶合成は少なく物性測定もあまり進んでいません。鉄系超電導物質の化学組成が複雑なうえ、薄膜作製の過程で安定な状態が保たれにくいのが原因ですが、細野教授らは薄膜作製に適した化学組成を選択しレーザーパルス堆積法を用いて、良質の単結晶薄膜を作製することに成功しました。 超電導を示す単結晶薄膜が得らるようになったことでデバイスへの応用が検討され始め、新物質の合成や物性測定、特性評価が帆ナ核化すと予想されています。 本研究成果は、応用物理学会の欧文速報誌に、2008年9月19日公開されました。 |
Appl. Phys. Express 1, 101702 (2008) Superconductivity in Epitaxial Thin Films of Co-Doped SrFe2As2 with Bilayered FeAs Structures and their Magnetic Anisotropy 論文を閲覧される場合は 下のリンクをご利用下さい。 doi:10.1143/APEX.1.101702 |
|
| 2008/ 9/ 1 | 日本経済新聞 平成20年 9月 1日(月) 化学工業日報 平成20年 8月29日(金) ・ 第1面,第4面 Journal of Physcal Society of Japan 注目論文(2008年5月号,6月号,7月号) |
|
| 細野・神谷研究室 | 日本経済新聞<朝刊> 平成20年 9月 1日(月) | |
|
鉄系超電導物質 臨界温度を高く |
||
| 化学工業日報 平成20年 8月29日(金) 第1面 | ||
|
文科省 鉄系新超伝導材料の応用研究を加速 |
||
| 化学工業日報 平成20年 8月29日(金) 第4面 | ||
|
応用物理学会 秋季講演会 鉄系高温超伝導体、窒化半導体で特別企画 -細野、中村教授ら第一人者が講演- |
||
| Journal of the Physcal Society of Japan 注目論文 | ||
| 7月号 「遍歴反強磁性体から非従来型超伝導へ:NMRで見た鉄系高温超伝導体LaFeAs(O1-xFx)」 J. Phys. Soc. Japan 77 (2008) 073701 / doi:10.1143/JPSJ.77.073701 |
||
|
"Evolution from Itinerant Antiferromagnet to Unconventional Superconductor with Fluorine Doping in LaFeAs(O1-xFx) Revealed by 75As and 139La Nuclear Magnetic Resonance " |
||
6月号 「鉄を含む新型高温超伝導体の超伝導ギャップと擬ギャップの直接観測に成功」 J. Phys. Soc. Japan 77 (2008) 063708 / doi:10.1143/JPSJ.77.063708 |
||
|
"Superconducting Gap and Pseudogap in Iron-Based Layered Superconductor La(O1-xFx)FeAs " |
||
5月号 「新超伝導体の母物質LaOFeAsの結晶構造と磁気的秩序を理論的に予測」 J. Phys. Soc. Japan 77 (2008) 053709 / doi:10.1143/JPSJ.77.053709 |
||
|
"A Possible Ground State and Its Electronic Structure of a Mother Material (LaOFeAs) of New Superconductors" |
||
|
<関連記事> オキシニクタイド超伝導シンポジウム 2008年 6月 国内シンポジウム 「高温超伝導体研究の新境地 ~新物質を徹底的に解明する~」(6月8日) 国際シンポジウム "International Symposium on Fe-Oxipnictides Superconductors"(6月28日,29日) |
||
細野秀雄 教授が発見した鉄系新型超伝導体に大きな注目が集まっています。 細野教授らの研究グループが論文を投稿した Journal of the Physical Society of Japan では、3ヶ月連続で注目論文に選ばれました。 文部科学省が来年度から「新規超電導物質の探索と物性解明」への取り組みを決め、新系統超電導物質の応用への展開を見据えた研究開発が推進されるなど関心の高さが伺えます。 また、2008年2月23日に鉄系新型高温超伝導体が発表されて以来、 世界的に活発な研究が始まり、2008年6月に日本で「オキシニクタイド超電導シンポジウム」(JST主催の国内及び国際緊急シンポジウム)が開催されたのを皮切りに、8月には第25回低温物理国際会議と超電導応用国際会議(ASC08) でそれぞれ緊急シンポジウムやランプセッションが行われています。 また、9月2日から始まった応用物理学会第69会学術講演会では特別企画として鉄系新型高温超伝導体のセッションが行われるだけなく、セッション以外にも鉄系新型高温超伝導体関連の多数の発表があり、日本経済新聞や化学工業日報などの新聞でも紹介されるなど大きな注目が集まっています。 |
||
| 2008/ 8/29 |
日経産業新聞<朝刊> 平成20年 8月29日(金) | |
| 松本研究室 |
半導体装置で液体の膜蒸着 「イオン液体」活用 高性能燃料電池に道 |
|
松本准教授らのグループが半導体製造装置で液体の膜を蒸着する技術(イオン液体の成膜技術)の開発に成功しました。 この新技術は、「イミダゾリウム系」のイオン液体を浸透させたシリコン微粒子を照射し、通常では蒸発することのないイオン液体を蒸発させて基板上に蒸着させることに成功したものです。 イオン液体には通電性があり、燃料電池などの電解質への利用が期待されている。現在の燃料電池では電極の間に電解質を流し込む必要があるが、新技術では成膜装置内で電極と電解質を一貫生産することが可能になり、装置内で真空を保ったまま電解質の化学合成と薄膜の積層が可能になるだけでなく、ナノスケールの微細なパターニングが実現できるのではないかと期待が高まっています。 |

|
|
| 2008/ 8/25 |
日経新聞<朝刊> 平成20年 8月25日(金) |
|
| 原研究室 |
稲わら・廃材からバイオ燃料 非食料でも安く製造 - コスト穀物並み - |
|
原教授が開発した固体酸触媒が、バイオ燃料生成の触媒として従来の硫酸法に代わる新方法として注目された記事が新聞に掲載されました。 非食料系バイオ燃料は雑草や廃木材、農業廃棄物等を原料に用いることができ、穀物価格の上昇で批判が上がっている食料系バイオ燃料に代わって普及が期待されていますが、高価い生産コストが課題になっています。 非食料系バイオ燃料は植物のセルロースを糖化(糖に分解)してエタノールを生成していますが、現在行われている酵素法(酵素でセルロースを分解する)や硫酸法(硫酸を触媒にして分解する)は、分解反応の前処理や後処理に手間やコストがかかり、食料系バイオ燃料よりも高い生産コストが必要です。 |

|
|
| 工業的にはセルロースの分解反応が短時間で済む硫酸法で大量生産が行われていますが、セルロースを糖化した糖液から硫酸を分離・回収するコスト低減が容易ではありません。 原教授が開発した固体酸触媒を利用する固体酸触媒法は、硫酸に匹敵する触媒性能(分解速度)を有し、分解反応の前後に処理が不要で、セルロースの糖化を安価で高効率に行なえることから、非食料系バイオ燃料でも食料系と同等まで生産コストが低減出来ると期待されています。 また、セルロースを分解した糖はバイオ燃料(エタノール)だけでなく、医薬品や樹脂の原料にも転用できるため、石油に頼る化成品の代替になるとして化学メーカーも固体酸触媒に注目しています。 |
||
| 2008/ 8/14 | 日経産業新聞<朝刊> 平成20年 8月14日(木) | |
| 近藤・中村研究室 |
半導体結晶の原子振動 リアルタイムで観測 - たんぱく質に応用も - |
|
中村一隆 准教授らの研究グループが半導体結晶内の原子振動をリアルタイム観測することに世界で初めて成功しました。 結晶を構成している原子は熱エネルギーによって恒に動いて(振動)しています。その振動は振動周期がピコ秒(10兆分の1秒)以下と短く、変位量がピコメートル(10兆分の1秒メートル)程度と極端に小さな振動で、振動の様子を直接計測することはほとんど不可能でした。 |
|
|
中村 准教授らは、原子の振動周期よりも短い時間で計測が可能なフェムト秒時間分解X線回折法(世界最短の極短パルスX線(時間分解能200フェムト秒(50兆分の1秒)によるX線回折)の開発に成功し、原子が振動しているピコ秒以下の時間スケールで、振動の様子をリアルタイム計測することに世界で初めて成功しました。 フェムト秒時間分解X線回折法による超高速構造解析の実現は、化学反応や物質の相転移現象などのダイナミクス(原子や分子間の結合状態の変化)の解明において重要な役割を持っており、たんぱく質の機能発現機構(分子の構造変化により機能が発現すると考えられている)の解明が可能になると期待されています。 本研究成果は、米国物理学協会の学術雑誌「Applied Physisl Letters」に 2008 年 8月13日(米国時間)公開されました。 |
Applied Physics Letters 93, 061905 (2008) Femtosecond time-resolved x-ray diffraction from optical coherent phonons in CdTe(111) crystal 論文を閲覧される場合は 下のリンクをご利用下さい。 doi:10.1063/1.2968212 |
|
|
<関連記事> 東京工業大学ホームページ「最近の研究成果」 平成20年 8月12日掲載 |
||
|
半導体結晶の原子運動をリアルタイムで追跡 -フェムト秒時間分解X線回折を用いて3ピコメートルの原子変位量を計測- |
||
| 2008/ 8/14 |
日刊工業新聞 平成20年 8月14日(木) |
|
| 原研究室 |
完全カーボンニュートラル バイオ燃料用新触媒に期待 |
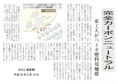
|
原教授との研究グループがバイオエタノール燃料用の新触媒(エコ固体酸触媒)の開発と量産に成功しました。 これは原「エコ固体酸触媒」プロジェクト(神奈川科学技術アカデミー(KAST)創造展開プロジェクト)の研究成果で、硫酸に匹敵する触媒性能を持つ固体強酸を開発し、硫酸触媒を代替することで環境負荷を最小限にする省エネ触媒を創成することを目指したもので、今後は工業化する研究が始まる予定です。 従来の硫酸触媒ではバイオエタノール燃料を生成した後に、後処理(硫酸を中和して溶液から分離)の必要があり、生成したバイオ燃料の3割以上のエネルギーを消費していましたが、新触媒は硫酸と同等の触媒性能を持つ固体酸触媒であるため、反応後の触媒が溶液中に沈殿して分離することが容易であり、特別な後処理が不要なためエネルギー消費が発生しません。 バイオエタノール燃料はカーボンニュートラル(二酸化炭素の排出量と吸収量の収支がゼロとなること)の代表例とされていますが、従来の硫酸触媒による生成法では後処理のエネルギー消費が原因でカーボンニュートラルを達成することはできず、逆に環境負荷を増やしてしまいます。 しかしながら、新触媒は後処理不要で生成工程でエネルギー消費がほとんど無い環境低負荷な触媒であり、ほぼ完全なカーボンニュートラルが実現可能であると期待されています。 |
||
| 2008/ 7/30 |
化学工業日報 平成20年 7月30日(水) |
|
| 原研究室 |
セルロースのバイオ燃料化 固体酸触媒法に期待高まる エネルギーコスト大幅減 反応後の触媒 簡単に回収、そのまま再利用 |
|
原教授が開発した固体酸触媒が、バイオ燃料生成の触媒として従来の硫酸法に代わる新方法として注目されています。 古くから生産されているバイオ燃料はトウモロコシや小麦、サトウキビ等の植物を原料とするる食料系バイオ燃料ですが、昨今の食糧問題で食用作物以外を原料に用いたバイオ燃料の生産技術の開発が進められてきました。 その一つが雑草や廃木材、農業廃棄物等の非食料系植物を原料とするセルロース系由来バイオ燃料です。 |

|
|
現在行われているセルロース系由来バイオ燃料の生産には濃硫酸を用いた硫酸法が用いられており、商業的な大型プラントも稼働していますが、反応後に糖化溶液(セルロースを糖化した溶液)と触媒の濃硫酸を分離・回収し、反応後に薄まった硫酸を濃縮して再び濃硫酸に戻すプロセスが必要であり、回収と再利用のプロセスに起因する環境・エネルギー面の問題を抱えています。 原教授が開発した固体酸触媒は硫酸を超える触媒性能を持ち、また固体であることから反応後の糖化溶液から分離・回収することがが簡単なだけでなく、回収した固体酸触媒は触媒性能が低下しないため、そのまま繰り返し使用可能で、硫酸法に比べてエネルギー消費を大幅に低減しつつ高効率で連続的にセルロースの糖化が行なえる優れた触媒です。 固体酸触媒法は未だ研究段階の技術で工業プラント等での大量生産の実績はありませんが、非食料系バイオ燃料(セルロース系由来バイオ燃料)の量産技術として工業化が期待されており、今後、産学連携などを通じて具体化されていくことになりそうです。 |
||
| 2008/ 7/15 |
日経産業新聞<朝刊> 平成20年 7月15日(火) | |
| セキュアマテリアル 研究センター |
超微粒子混ぜセメント 曲げ強度2倍以上に | |
セキュアマテリアル研究センター協力研究部門の坂井教授らのグループが、セメントに酸化ケイ素の超微粒子と高分子分散剤を混合して、従来の2倍以上の曲げ強度を有するセメントを開発することに成功しました。 |
||
液状のセメントは、固まった後に未反応の水分が抜けて空隙となり強度低下の原因となりますが、坂井教授らのグループが開発したセメントは必要な水分量が少なく、それに応じて空隙も少ないために強度低下が抑えられています。 従来のセメントと同等の圧縮強度を有し、さらに曲げ強度が2倍以上であるため、揺れや歪みに対する耐久性が必要とされる壁や屋根、地中に埋める下水管などに利用できると考えられ、企業と組んで3年後の実用化を目指して開発が進められています。 |
|
|
| 2008/ 7/ 2 |
日経産業新聞<朝刊> 平成20年 7月 2日(水) | |
| 細野・神谷研究室 |
高温超伝導 新材料、大電流に対応 イットリウム系並み 米強磁場研が確認 |
|
細野教授らのグループが発見した「鉄ニクタイド系高温超伝導材料」が、従来の代表的な高温超伝導材料(イットリウム系)並みの大電流を流せることを米国立強磁場研究所が確認しました。 検証実験は、磁力をかける「磁化法」で 1cm2 に流れる電流密度を測定したもので、多結晶試料中の結晶粒内を流れる電流密度は約1000万アンペア(絶対温度 4.2度)でした。 多結晶試料中の結晶粒界に不純物が存在するために、試料全体での電流密度は 4000アンペアに低下しましたが、不純物を除去することで結晶粒内と同程度まで電流密度を高められるとみられています。 イットリウム系の高温超伝導材料の電流密度は発見当初に不純物の無い多結晶試料で 100アンペア程度であり、電流密度を高めるために結晶粒同士の角度のズレを無くす必要がありますが、「鉄ニクタイド系高温超伝導材料」は結晶粒の角度のズレによる影響が少なく、粒界に存在する不純物の問題を克服できればイットリウム系よりも安価に線材を作成可能であると考えられ、実用化に向けて期待が高まっています。 |

|
|
| 2008/ 6/23 |
産経新聞 平成20年 6月23日(月) | |
| 細野・神谷研究室 |
”門外漢”が常識破る さらに広がる探求心 新たな高温超電導物質を発見 |

|
細野教授にスポットを当てた特集記事が産経新聞I掲載されました。 細野教授は透明アモルファス酸化物半導体で透明で曲げられる高性能トランジスタを実現し、絶縁体のセメント物質12CaO・7Al2O3(C12A7)を半導体や金属同様の導電体に変えることに成功しました。また、今年2月には鉄系統の新型高温超伝導体を発見、金属,銅酸化物系に続く第3の超電導物質として世界的な研究競争の発端になりました。 記事中では、細野教授のユニークな研究スタンスや限りない探求心、また科学を目指す切っ掛けになった少年時代のエピソードが紹介されています。 |
||
| 2008/ 6/13 | 科学新聞 平成20年 6月13日(金) 日経産業新聞 平成20年 6月 4日(水) |
|
| 伊藤・谷山研究室 | 科学新聞 平成20年 6月13日(金) |  |
|
環境に優しいコンデンサー材料を 巨大な電気歪特性を示す 鉛を含まない物質発見 |
||
|
伊藤教授らの研究グループの研究成果によって、環境に優しく幅広い環境に柔軟に対応できる非鉛系のグリーン材料開発に大きな発展が期待されます。 |
||
| 日経産業新聞 平成20年 6月 4日(水) |  |
|
|
電圧変形材料、鉛含まず -プリンタヘッド向け 代替の可能性- |
||
|
伊藤教授らの研究グループ(JST、東工大・腰原教授、東大・常行教授)が新しいタイプの圧電材料(電圧変形材料)を開発しました。 |
||
| 科学技術振興機構(JST)と東工大と東大の共同発表 平成20年 5月30日(金) | ||
|
大きな電気歪(ひずみ)特性を持つ非鉛系物質を発見 -環境に優しいコンデンサーなどの材料に- |
||
| 圧電材料はアクチュエータとして精密機械の位置合わせなどに利用されていますが、現在主流のPZT (鉛・ジルコニア・チタン酸化物)は、鉛を含むために世界的に規制が強化されており、代替材料の開発が急がれていました。 伊藤教授らの開発した圧電材料は、チタン酸バリウム結晶中のバリウムの一部をカルシウムに置換したもので、PZTよりも非常に高い電気歪特性(圧電性)を持っています。 また本研究で、チタン酸バリウム結晶内に非平衡状態を強制的に作り出すことにより、圧電性の制御が可能になることが明らかとなり、アクチュエータ素子材料の非鉛化やコンデンサーなどの改良だけでなく、非鉛系の環境に優しい新規の圧電材料開発に繋がるのではないかと注目が集まっています。 本研究成果は、米物理学会誌「Physical Review Letters」に 2008 年 6月 6日(米国時間)公開されました。 |
Physical Review Letters 100, 227601 (2008) Anomalous Phase Diagram of Ferroelectric (Ba,Ca)TiO3Single Crystals with Giant Electromechanical Response 論文を閲覧される場合は 下のリンクをご利用下さい。 doi:10.1103/PhysRevLett.100.227601 |
|
| 2008/ 6/12 |
朝日新聞<朝刊> 平成20年 6月12日(木) | |
| 和田研究室 | 都市機能、日頃から対策を | |
和田章 教授が中国・四川大地震の現地調査を行ないました。 調査報告によると、80~90年代に建てられた4、5階建ての校舎や住宅が鉄筋コンクリートで作られた柱など一部を残して全壊、あるいは半壊していて、これらの建物が倒壊した要因は主に「れんが柱」であったことと「コンクリート床板の結合が不十分」であったことの2点考えられるとしています。 |
||
| 都市部では高層ビルなど壊れていない建物も多く、中国の技術が低いわけではなく、さまざまなフの要因がかけ合わさって大きな被害を招いたとみられています。 一方、日本でも住民の合意形成が難しい分譲マンションなどの耐震補強が進んでおらず、古い校舎や病院もたくさん残っているので安心は出来ません。 和田教授は「暮らしが便利になった分、社会は脆く壊れやすくなっている。通信回線や電気が止まれば都市機能はマヒする。今のうちから対策をとらなくてはならない」と警鐘しています。 |

|
|
| <関連記事> 日経新聞<夕刊> 平成20年 5月27日(火) 「れんが柱」が大きな被害」 |
||
| 2008/6/ 9 |
セメント新聞 平成20年 6月 9日(月) | |
| セキュアマテリアル 研究センター |
東京コンクリート診断士会(小野定会長)は、6月4日に開催した総会で、2008年度活動計画に応用セラミックス研究所との共同研究テーマである「セキュアマテリアル」に関するワークショップの開催を盛り込みました。 |
|
| 2008/6/ 9 |
セメント新聞 平成20年 6月 9日(月) | |
| 林(靜)研究室 | 林 静雄 教授が会長を務める「日本圧接協会」が「日本鉄筋継手協会」へ組織名称が変更されることになりました。 日本圧接協会は、主にガス圧接の技量向上・品質確保を目的に63年に設立され、99年からは全ての鉄筋継手を事業対象にしていました。 |
|
林 静雄 教授は「今回名称を変更することとなったが、事業内容としては従来通り、わが国の鉄筋継手の品質管理・向上に取り組んでいくこととなる。みなさんの協力を得て一歩一歩進めていきたい」と述べました。 |
|
|
| 2008/ 6/ 6 | 科学新聞 平成20年 6月 6日(金) | |
| 細野・神谷研究室 | 科学新聞 平成20年 6月 6日(金) |  |
|
新超電導体の母物質 LaOFeAs 結晶構造と磁気秩序 -理論的に予測- |
||
|
鉄系統高温超電導体 LaOFeAs の結晶構造と磁気秩序を第一原理計算によって理論的に予測することに成功しました |
||
|
<関連記事> 科学技術振興機構(JST)と東京工業大学の共同発表 平成20年 2月18日(月) |
||
|
新系統(鉄イオンを含む層状化合物)の高温超伝導物質を発見 -高温超電導材料の新鉱脈の発掘- |
||
|
<関連記事> 日経ビジネス・オンライン 平成18年 7月19日(水) |
||
| 東工大、鉄酸化物系の新しい超伝導体を発見 | ||
細野秀雄 教授らの研究グループ(東京工業大学、産業技術総合研究所、北陸先端科学技術大学院大学)が第一原理計算によって、新型超電導体 LaOFeAs の結晶構造と磁気秩序を理論的に予測することに成功しました。 |
||
新型超電導体は銅酸化物超電導体と類似性が強い層状構造を有していますが、結晶構造では遷移金属の周囲の陰イオン配置の対称性が異なり、また、強磁性の鉄が主体になっている点が大きく異なっています。 母相の LaOFeAs層が超電導体ではなく、キャリアをドープすることで超電導が発現することは、銅酸化物超電導体と類似しています。 新型超電導体が銅酸化物超電導体と同様の超電導機構を持つと類推すれば、超電導発現機構の解明のために LaOFeAs母相の基底状態を明らかにする必要がありました。 今回、理論的な予測に成功したことで、LaOFeAsと類似構造を持ちながらキャリアドープの必要がない超電導物質 LaOFeP等との比較が可能となり、超電導発現機構の解明に迫る大きな一歩になるのではないかと考えられています。 本研究成果は、日本物理学会の英文学術誌(JPSJ) の2008年5月号に掲載されました。 |
J. Phys. Soc. Japan 77, 053709 (2008) A Possible Ground State and Its Electronic Structure of a Mother Material (LaOFeAs) of New Superconductors 論文を閲覧される場合は 下のリンクをご利用下さい。 doi:10.1143/JPSJ.77.053709 |
|
| 2008/ 6/ 2 |
日経新聞<朝刊> 平成20年 6月 2日(月) | |
| 細野・神谷研究室 |
東工大発の高温超電導 新素材、中国が猛追 実用化へ研究競争 -日本側、優位確保へ支援- |
|
細野秀雄 教授らの研究グループが発表した鉄系統の新型高温超伝導体をめぐって、日本と中国の間で研究競争が激化しています。 |
||
2月の発表以来、中国が改良して超電導転移温度を高める成果を挙げているためで、論文投稿前に研究結果を速報できるサイト(プレプリントサーバー http://arxiv.org/archive/cond-mat)に新型高温超電導材料についてのリポートが毎日3~5件掲載される中で、その七割が中国という状況になっています。 北沢宏一JST理事長は「中国が先に改良した材料や応用の特許を取得する可能性がある」と危機感を募らせ、JST主催の国内シンポジウム(2008年6月8日開催)と高温超電導研究の世界的権威8人を招く国際シンポジウム(2008年6月28日~29日開催)を緊急開催して日本が研究開発の中心であることを内外に示すことになりました。 また、今年度中に1課題あたり数百万円~2千万円の研究支援を行ない、日本での研究開発のすそ野を広げて研究優位の確保と重点的な研究開発が進められるようです。 |

|
|
| 2008/5/27 |
日経新聞<夕刊> 平成20年 5月27日(火) | |
| 和田研究室 | 「れんが柱」が大きな被害 | |
中国・四川大地震の現地調査を行なった和田章 教授が、被災地で建物の倒壊我が相次いだ原因は「壁だけではなく柱もれんがを積み上げただけの建物が多かった」と指摘しました。 |
||
倒壊を免れた建物の中には壁などがれんが造りでも、柱や梁は鉄筋コンクリートの建物が目立ったと報告しています。 和田教授は現地の状況を鑑みて「れんがを一切使わない工法を押しつけるのは非現実的。梁や柱など建物の骨格には鉄筋コンクリートを用い、れんがは二次的に使うなどの対策が有効」と提言しています。 |

|
|
| 2008/5/26 |
日経産業新聞 平成20年 5月26日(月) | |
| セキュアマテリアル 研究センター |
探訪・イノベーション拠点 東京工業大学 セキュアマテリアル研究センター |
|
|
「安全に壊れる」素材追求 |
||
中国・四川大地震では崩れ落ちた建物のがれきの下敷きになって多くの方が亡くなりました。 本来は人を守るべき建物が逆に人命を奪ってしまったのです。 もしも全てのがれきが砂のように細かく壊れてくれたら、前身が埋まっても助かったかもしれない・・・ |
||
セキュアマテリアル研究センターでは、「これからの材料は、安全な形に壊れることが性能の一つになる」ことを視野に入れて「絶対に壊れない」から「安全に壊れる」新材料を目指して研究を行なっています。 例えば、宇宙空間に漂っているスペースデブリ(宇宙塵)が宇宙ステーションや人工衛星に衝突すれば大きな損傷を受けますが、かといってデブリを跳ね返しただけでは飛ぶ方向を変えるだけでは別の人工衛星などにぶつかりかねません。 セキュアマテリアル研究センターが研究している新材料は、強い衝撃が加わると巧みに壊れ、自らが安全に壊れながら、衝突したデブリも砕いたり運動エネルギーを分散させて被害が全体に及ばないように「一部を壊して全体を守る」ことが可能になると考えられています。 |

|
|
| 2008/ 5/16 |
「鉄系超電導体」がNature,Science 等のニュース・解説記事に相次いで掲載! | |
| 細野・神谷研究室 | 鉄系超電導体に関するニュースを目にする機会が多くなっている中、英国科学会誌「Nature」と米国科学会誌「Science」等にニュースや解説記事が相次いで掲載されました。 鉄系超電導体への注目度と期待の高さが伺えます。 |
|
| Nature, vol.452, 914 (24 April 2008) |  |
|
| Editorials: "Superconductors redux" | ||
| Nature, vol.452, 922 (24 April 2008) |  |
|
| News: "Arsenic hears up iron superconductors" | ||
| Science, vol.320, 432-433 (25 April 2008) |  |
|
|
This week news: "New Superconductors Propel Chinese Physicists to Forefront" |
||
| Science, vol.320, 870-871 (16 May 2008) |  |
|
|
News Forcus: "The Hot Question: How New Are The New Superconductors?" |
||
| Physics Today , 11-12 (May 2008) |

|
|
| "New family of quaternary iron-based compounds superconducts at tens of kelvin" | ||
|
「Nature」(電子版)論文掲載おめでとうございます! 2008年4月24日(英国時間)公開 |
||
| 2008/ 5/12 | 産経新聞 平成20年 5月12日(月) 朝日新聞 <朝刊> 平成20年 4月28日(月) 読売新聞 <朝刊> 平成20年 4月27日(日) 日経産業新聞,日刊工業新聞 平成20年 4月24日(木) |
|
| 細野・神谷研究室 | 産経新聞 平成20年 5月12日(月) | |
|
銅酸化物以外で最高温度の超電導物質 |
||
| 朝日新聞<朝刊> 平成20年 4月28日(月) | ||
|
超電導になる温度 4万気圧で11度上昇 |
||
| 読売新聞<朝刊> 平成20年 4月27日(日) | ||
|
鉄系高温超電導物質に新たな性質 |
||
| 日経産業新聞 平成20年 4月24日(木) |  |
|
|
鉄系加圧で超電導 |
||
| 日刊工業新聞 平成20年 4月24日(木) |

|
|
|
4万気圧で抵抗ゼロ -高温化に可能性- |
||
| 細野教授らの研究グループが研究している鉄を含む高温超伝導体に圧力を加えると超電導転移温度が高くなることが発見されました。 加圧下では結晶格子の状態が変り原子間の距離が短くなることから、常圧でもランタンなどをより小さな原子に置換して原子間距離を短くすれば、さらに高温で超電導になる物質が創成できると考えられ、新物質の発見にも応用できる成果に注目が集まっています。 本研究成果は、英国科学会誌「Nature」(オンライン版)に、2008 年 4月23日(英国時間)に公開され、「日経産業新聞」「日刊工業新聞」(2008年4月24日)や「読売新聞」(2008年4月27日),「朝日新聞」(2008年4月28日),「産経新聞」(2008年5月12日)でも紹介されました。 |
Nature (電子版) (Published online: 23 April 2008 | doi:10.1038/nature06972 ) Superconductivity at 43 K in an iron-based layered compound LaO1-xFxFeAs 論文を閲覧される場合は 下のリンクをご利用下さい。 doi:10.1038/nature06972 |
|
| 2008/4/23 |
JSTサイエンスポータル 平成20年 4月23日(水) | |
| セキュアマテリアル 研究センター |
セキュアマテリアルの提言-安心安全な材料を目指して | |
2008年3月25日に開催された「統合研究院・セキュアマテリアル国際ワークショップ」(主催:東工大統合研究院、共催:応セラ研セキュアマテリアル研究センター)について、サイエンスポータルのオピニオン(4月23日版)に 石川正道 教授(東工大・統合研究院)の記事が掲載されました。 国際ワークショップで取上げたテーマ「モビリティ(自動車)社会の安全と安心」の意味に触れ、二酸化炭素の排出に伴う地球温暖化や資源枯渇など世界の持続的発展の障害となるグローバルな面と、自動車社会がもたらす交通渋滞・事故や大気汚染問題など地域の安心安全を脅かすローカルな面の全くスケールが異なる2つの面が材料開発に関連して浮き彫りになったことが紹介され、この社会の持続的発展に伴う2つの問題点を克服する可能性として、軽量・リサイクル・安全を同時に満たすことのできるセキュアマテリアル材料の導入について提言されています。 |
||
|
(JSTサイエンスポータル・オピニオンの当該記事へのリンク) |
||
| 2008/ 4/ 1 |
NHK教育テレビ 「サイエンスZERO」 2008年 4月 6日(日)放映予定 テレビ東京 「ニュース・ワールドビジネスサテライト」 2008年 4月 8日(火)放映予定 |
|
| 細野・神谷研究室 | NHK教育テレビ「サイエンスZERO」(2008年 4月 6日放映予定)とテレビ東京「ニュース・ビジネスサテライト」(2008年 4月 8日放映予定) で 細野秀雄 教授 の研究成果に関する特集が放送されます。 どちらもこれから放映されますので、ご興味がおありの方は是非番組をご覧下さい。 |
|
|
番組名:NHK教育テレビ「サイエンスZERO」 |
||
| 番組内の「科学∞(無限大)」コーナーで「先端科学でメダルを狙え」というテーマの特集があり、細野教授の第三の超電導物質発見に関するニュースが紹介されます。 | ||
|
番組名:テレビ東京「ニュース・ワールドビジネスサテライト」 |
||
| 番組内で「環境問題を支えるレアアース 最新事情」というテーマの特集が組まれ、細野教授の研究成果が紹介されます。 | ||
| 2008/ 3/30 |
読売新聞<朝刊> 平成20年 3月30日(日) | |
| 細野・神谷研究室 |
資源難 身近な元素活用を 細野・東工大教授が講演 |
|
3月17日に「東京テクノ・フォーラム21」研究交流会で行われた 細野秀雄 教授の講演が紹介されました。 資源難が叫ばれる中、レアメタルの需給が増大しているために価格が高騰し、商品開発に大きな影響を与えています。 事態を打開するには、レアメタルの使用削減やリサイクル、代替元素の使用などの手段がありますが、抜本的な解決にはなっていません。 |
||
細野教授は講演で、(クラーク数が大きい)ありふれた元素に新機能を見いだす必要性を訴え、研究成果のセメント材料物質「C12A7」がナノ構造の工夫で様々な新機能を発現している事例を紹介し、「常識にとらわれず、これまでの物質のイメージを覆す挑戦的な研究が次々と行われる事で、資源難の時代を乗り切る新技術が生まれてくるはずだ」と提言しました。 |
|
|
| 2008/ 2/19 | 新聞各紙 平成20年 2月19日(火) ~ | |
| 細野・神谷研究室 | 朝日新聞<朝刊> 平成20年 3月17日(月) |  |
|
超電導フィーバー再び? -「室温」へ広がる選択肢- |
||
|
磁性のある鉄を含んだ系での超電導物質は、磁石と相性が悪い弱点を克服する可能性があるだけでなく、これまで新物質探索の対象にならなかった金属元素や希土類元素の組合わせが可能になるなど、新物質探しの選択肢の幅を大きく拡げました。 「今までの高温超電導物質とは全く違う新物質と考えられる」という評価もあり、新型超電導物質の探求が活気づいてきています。 |
||
| 日経産業新聞 平成20年 2月29日(金) |  |
|
|
新たな超電導物質発見 新種探索、高まる気運 |
||
| 東京新聞<朝刊> 平成20年 2月26日(火) |

|
|
|
超電導 第3の物質発見 -高温での転移に期待- 酸化物系でも金属系でもない第三の化合物系の発見により 壁に突き当たっていた超電導物質の開発に展望が 開けるのではないかと期待されています |
||
| 日経産業新聞 平成20年 2月26日(火) | ||
|
新高温超電導物質 JSTが共同研究 -日本発の実用化支援- |
||
| 日刊工業新聞 平成20年 2月25日(月) | ||
|
対照的な研究支援 特別研究チームが発足するJST理事長のコメント |
||
| 読売新聞<朝刊> 平成20年 2月24日(日) |  |
|
|
鉄系の高温超電導物質 -東工大チームが発見- |
||
| 朝日新聞<朝刊> 平成20年 2月19日(火) |  |
|
|
超電導の新型物質発見 -鉄を含む化合物- |
||
| 毎日新聞<朝刊> 平成20年 2月19日(火) |  |
|
|
鉄化合物で超電導 -高温記録へ「新鉱脈」か- 従来、超電導に不向きとされた鉄を含む化合物での超電導 |
||
| 日経新聞<朝刊> 平成20年 2月19日(火) | ||
|
新タイプの超電導物質 -不向きの鉄含む- |
||
| 日経産業新聞 平成20年 2月19日(火) |  |
|
|
高温超伝導体に新種 -鉄を含む化合物- |
||
| 日刊工業新聞 平成20年 2月19日(火) |  |
|
|
高温超伝導の新物質発見 -磁性系、鉄が主成分- |
||
| 科学技術振興機構(JST)と東京工業大学の共同発表 平成20年 2月18日(月) | ||
|
新系統(鉄イオンを含む層状化合物)の高温超伝導物質を発見 -高温超電導材料の新鉱脈の発掘- |
||
|
<関連記事> 日経ビジネス・オンライン 平成18年 7月19日(水) |
||
| 東工大、鉄酸化物系の新しい超伝導体を発見 | ||
| 細野秀雄 教授(フロンティア研究センター) らの研究グループが鉄を含む超電導物質の作成に成功しました。 これまで超電導にならないと考えられていた鉄を含んだ化合物での超電導体発見は、「金属系」,「銅酸化物系」に続く第3の高温超電導物質になるのではないかと考えられています。 |
||
細野教授らの研究グループが数年前から注力しているセメント物質C12A7 (12CaO・7Al2Ol3)は典型的な絶縁体でしたが、細野教授らの研究によって半導体へ変えることに成功し、続いて電気電導性と超電導性を発現させてセメントを金属へ、そして超電導体へと変えることに成功してきました。 今回の鉄を含んだ高温超電導物質の発見は、ナノ構造の工夫次第で従来不可能と考えられていた新しい機能を発現できることを明快に示した結果であり、新たな高温超電導物質の足がかりとなる大きな成果に期待が集まっています。 本研究成果は、米化学会誌(オンライン版)に、2008年2月23日(米国時間)に公開されました。 |
J. Am. Chem. Soc., ASAP Article (Web Release Date: Feb. 23, 2008) Iron-Based Layered Super-conductor La[O1-xFx]FeAs (x=0.05-0.12) with Tc = 26 K 論文を閲覧される場合は 下のリンクをご利用下さい。 doi:10.1021/ja800073m |
|
| 2008/ 1/ 1 | 科学新聞<夕刊> 平成20年 1月 1日(火) | |
| 近藤・中村研究室 |
衝撃圧縮過程を100ピコ秒で瞬間撮影 -物質破壊の様子観察- |

|
物が壊れる時には衝撃で物質が圧縮・変形し、破壊に至りますが全過程はごく短時間で起るために精密な測定は極めて困難でした。 中村一隆 准教授の参加する研究グループ(研究代表者:東工大 腰原教授)による研究成果はX線回折を瞬間測定(時間分解能100ピコ秒)を実現した画期的なもので、衝撃や損傷に強い材料の開発を行なう際の重要な技術になると期待されています。 |
||
| 2008/ 1/ 1 |
日経産業新聞 平成20年 1月 1日(火) | |
| 細野・神谷研究室 |
レアメタル 代替 で勝負 ありふれた元素が「変身」 電気通す「セメント」 |

|
細野秀雄 教授の研究グループによって電導性を始め様々な新機能を発現したセメント材料C12A7のように、安価な汎用材料で新機能を見いだす研究が盛んになっています。 レアメタルの価格が世界的な需給の増大や中国の輸出規制に伴って高騰している中、セメント材料のように簡単に手に入る資源でレアメタルを代替できるような新素材を作る研究が重要性を増してきました。 |
||
<TOPに戻る>